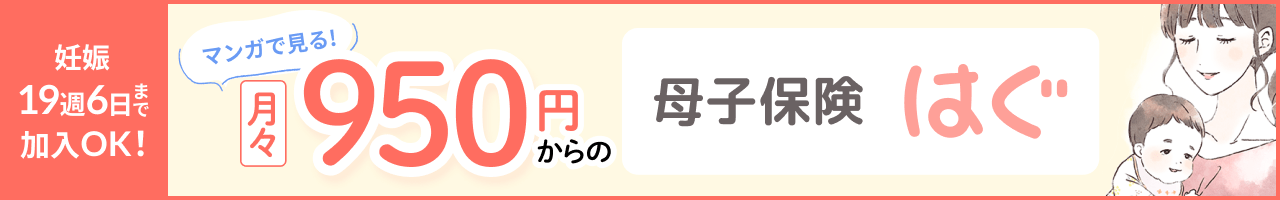出産育児一時金とは?出産時にもらえる手当金の情報を網羅的に解説!
出産時に利用できるお金には、主に「出産手当金」 と「出産育児一時金」の2つがあります。それぞれ全く異なる給付金 ですので、利用する際には両者の違いを理解し、正しく手続きを行う必要があります。本記事では、各手当金の対象者や支給される金額、必要書類などについて紹介します。出産を控えている方はぜひ参考にしてみてください。
- 出産手当金と出産育児一時金とは
- 出産手当金の概要
- 出産育児一時金の概要
- 出産育児一時金でよくある質問
- まとめ
出産手当金と出産育児一時金とは

出産手当金と出産育児一時金は名称が似ていますが、全く異なる給付金です。
大きな違いは対象者で、出産手当金は出産のために休業する健康保険加入者が対象となります。なお、自営業やフリーランスなどの、国民健康保険の加入者は対象となりません。
一方、出産育児一時金は妊娠4ヶ月以上の出産する全ての健康保険加入者・被保険者が対象となるという違いがあります。
出産手当金の概要
出産手当金は、出産のために会社を休む場合に利用できる給付金です。会社から給与が支払われなかった時に限りますが、勤務先の健康保険から支給されます。
出産手当金の対象者
出産手当金は、出産日以前42日(双子以上の多胎であれば出産日以前98日)から出産の翌日以後56日まで会社を休んだ健康保険加入者が対象となっています。
また、計算によって会社を休んだ日数分の金額が支給されます。
出産手当金で1日に支給される金額
出産手当金の1日あたりの金額は、健康保険加入期間が12ヶ月に満たない場合と12ヶ月を超えた場合で支給される金額が異なります。
健康保険加入期間が12ヶ月を超えた場合の1日あたりの金額は、以下で計算されます。
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷ 30日 ×(2/3)
また、支給開始日以前の健康保険加入期間が12ヶ月に満たない場合は、以下のうちいずれか低い額を使用して計算します。
ア.支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ.標準報酬月額の平均額
28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方
30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方
では、合計でどの位の出産手当金が給付されるか、計算してみましょう。ここでは、健康保険加入期間が12ヶ月を超えた場合とします。支給開始日以前に12ヶ月分の標準報酬月額がありますので、各月の標準報酬月額を合算して平均額を算出します。
例えば、3ヶ月分の給与が28万円で、9ヶ月分の給与が30万円の場合は、「(28×3+30×9)÷ 12 ÷ 30 × 2/3 × 98日」の計算式で64万2,765円の給付金を利用できます 。
出産手当金の手続き方法と必要な書類
出産手当金を利用するには、産休に入る前に出産手当金支給申請書をもらっておく必要があります。会社から渡される場合もありますが、自分で用意する必要がある場合には、加入している健康保険のホームページなどからダウンロード できます。
申請書類には自筆欄、医師・助産師の欄、事業主が記入する欄が存在し、記載が必要です。また、記述ミスや無記載の箇所があると手続きに時間がかかるため、抜け漏れのないように記載することが大切です。
資格喪失後(退職後)にも制度を利用できるケースがある
原則的に健康保険の加入者へ給付されますが、退職によって資格を喪失した場合などにも条件を満たせば継続的に給付を受けることが可能です。
一般的には以下の場合に制度を利用できます。
・資格を喪失した場合:前日まで (退職日)に継続して1年以上の被保険者期間があること(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)
・資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金は支払われません。
出産育児一時金の概要

出産育児一時金は、健康保険から受け取れる給付金の制度です。 出産は病気ではないため、健康保険が適用されませんが、出産育児一時金により健康保険より助成を受けることが可能となっています。
出産育児一時金の対象者
出産育児一時金の対象者は、健康保険の加入者 もしくは配偶者の健康保険の被扶養者となります。また、妊娠4か月(85日)以上で出産する人という条件も設けられています。
これらの条件を踏まえると、万が一流産・死産となってしまった場合にも、妊娠から85日を過ぎていれば 給付対象となるのです。
出産育児一時金で支給される金額
出産育児一時金は、子ども1人につき42万円が支給されます。ただし、特殊なケースもありますので併せて確認しておきましょう。
1.産科医療補償制度に加入していない病院で出産した場合は40.8万円の支給
2.付加給付金がある健康保険に加入している場合は42万円+付加給付金分
また、双子、三つ子などの場合には子どもの人数分の出産育児一時金が受け取れます。
出産育児一時金の手続き方法と必要な書類
出産育児一時金の申請手続きと必要書類は、受取方法によって異なります。各方法を以下で説明しますので、確認のうえ手続きを進めてください。
【直接支払制度を利用する場合】
1)出産予定の医療機関で直接支払制度の説明を受ける
2)「直接支払制度利用の合意書」に記入し、医療機関へ提出する
3)出産後、医療機関が支払機関経由で健康保険に出産育児一時金の請求をする
【受取代理制度を利用する場合】
1)出産予定の医療機関で受取代理制度が利用できることを確認する
2)自分の加入している健康保険から「出産育児一時金支給申請書(受取代理用)」を取り寄せて記入する。「受取代理人欄」は医療機関に記載してもらう。
3)必要書類(母子手帳や出産予定日のわかる書類など)とともに健康保険に提出する
4)出産後、医療機関が健康保険に出産育児一時金を請求する(差額がある場合は、差額のみを支払う)
【事後申請を利用する場合】
1)直接受取制度が利用できる医療機関の場合「制度を利用しない合意書」に記入する。
2)出産後の退院時に出産費用全額を支払う。
3)自分の加入している健康保険から「出産育児一時金支給申請書」を取り寄せ、必要書類(出生証明書や「直接受取制度を利用しない合意書」の控え、医療機関での領収書など)を準備する
4)必要書類とともに健康保険に提出、その後約2か月程度で指定金融機関に振り込まれる。
出産育児一時金で足りない場合は出産費貸付制度も利用可能
出産育児一時金で資金が足りない場合には、出産育児一時金の8割相当額を限度として、資金の無利子貸付を受けられる制度もあります。
こちらの制度は、被保険者または被扶養者対象で出産予定日まで1ヵ月以内の方、または妊娠4ヵ月以上で医療機関等に一時的な支払いを要する場合に利用可能です。出産費貸付金貸付申込書へ記入後、加入している健康保険 へ提出することで申し込めます。
出産育児一時金でよくある質問

出産育児一時金を利用する際、煩雑な手続きが必要となるため、不安に感じる方も多いでしょう。ここでは、出産育児一時金利用の際によくある質問について紹介します。
国民健康保険と健康保険両方の申請が可能?
国民健康保険と健康保険の両方を申請することは不可能です。どちらか一方の選択となります。
海外で出産した場合の一時育児金は?
海外で出産した場合でも、出産育児一時金を申請することが可能です。ただし、必要に応じて書類を用意する必要があり、主に以下が必要です。
1.出生した赤ちゃんが被保険者の被扶養者に認定されている場合
・医師・助産師の証明
・市区町村の証明
2.上記証明がない場合
・戸籍謄(抄)本
・戸籍記載事項証明書
・出生届受理証明書
・母子健康手帳
・住民票
3.出生したお子様が、被保険者の被扶養者ではないが日本国内に居住している場合
・日本国内の公的機関が発行する戸籍謄(抄)本等の出産の事実が確認できる書類
4.出生したお子様が、被保険者の被扶養者ではなく、海外に居住している場合または死産の場合
・現地の公的機関が発行する戸籍や住民票等の住民登録に関する書類
5.上記書類が添付できない場合
・加入している健康保険によって取り扱いが異なるので、確認しましょう。
本記事では「出産手当金」と「出産育児一時金」それぞれの概要などを紹介してきました。それぞれの違いを踏まえた上で必要な手続きを行う必要があります。
また、妊婦さん専用の保険である、母子保険はぐ+(プラス)の利用も検討してみてください。妊娠・出産期の入院や手術を保障し、生まれた瞬間から赤ちゃんを守る保障がつくことも特徴です。まずはかんたん診断から利用してみてください。